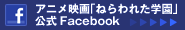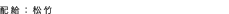[『ねらわれた学園』特別対談]中村亮介 × 氷川竜介 第五回
鮮やかな色彩の世界観と豊かな動きは
あの頃の心象風景と身体感覚を表現したもの
氷川:中村監督が得意とされる映像処理のことですが、この映画は全体がものすごく色鮮やかで、どのカットにも必ず光の乱反射のレインボーが入っていて、すごくキラキラした感じです。こうした処理を全編にかけるなど、映像面での狙いもお聞きしたいです。
中村:作業時間には限りがありますので全部がイメージ通りにいったかは別にして、作品の狙いでした。今回、この映画の技術的な目標として、「2Dのアニメの魅力ってそもそも何だろう」って考えたんです。それが、はっきり感じられる映画でありたいなと。アニメってもともと、全てが作為でできているものじゃないですか。偶然の入り込む余地が少ない表現だと思うんです。それならば、わざわざ絵で描く以上、リアルに描くことプラスα、思い切ってエモーショナルな部分を絵に乗せていきたいと思ったんです。それがこの作品には合っているだろうと。だから美術スタッフにまずお願いしたのが、「写真みたいに描かないでください」と。写真を簡略化した表現が背景なのではなく、あくまで絵画として考えてほしいと。だから壁一枚、天井一枚にも、それを「美しい」と感じた美術スタッフの思いがこもった背景になっているんです。キャラクターの動きに関しても、リアルな動きプラスα、気持ちが弾んでいる時は動きも大きく。そんなに飛んですごいなって感じてほしい動きは、ジャンプもより高く。リアルな表現をベースにしつつも、それをひとつ超えたところにある作画ならではの気持ち良さと、一方で非常に繊細な表現との対比を、この映画の表現の幅としてやっていきたいなと。あと、絵づくりの発想に関して言いますと、イラスト的、といいますか。僕は今はイラストレーターの時代だと思ってるんですけど、いわゆるBG(背景)にセル画が乗ったルックのビジュアルが、若い人にどれだけ指示されているのかな、という思いが前からあって。一枚一枚の絵を、思いきってイラスト的な発想でまとめてみる挑戦をしたんです。
氷川:この映画を観るという体験から何かを感じてもらいたいという姿勢ですよね。その体験性っていうことで言えば、中学生のころの自分って、もしかしたらこんなふうに世界をきらびやかにとらえていたのかもしれないなって思ったんです。色合いにしても、夕暮れは夕暮れらしく、月は月らしく、思春期は今よりもはるかにビビッドに見えてたかもしれないって・・・・・。
中村:おっしゃる通りです。そうやってキャラクターの心情や主観に沿って世界を描くことも、2Dのアニメだからこそできることかなと思うんですよ。僕がこの業界に入った頃は、一部のアート系アニメをのぞけば、ほぼ2Dだけがアニメを作る手法だったように思うんです。でも今は『009 RE:CYBORG』にしてもフル3Dであそこまでできる。あるいはFlashという方法もある。今の時代では、逆に僕らが“2Dでアニメを作る意味って何ですか?”って訊かれてるような気分になってるんです。だからこそ、“自分たちは2Dでしか表現できないアニメの魅力が好きだから、この手法をとっているんです”と、はっきり言えるようなアニメでありたいなと。
リアルを超えられる2Dのアニメの魅力を
はっきり意志表明する作品にしたかった
氷川:キャラクターの動きにしても、同じことを感じました。オーバーアクションと言うか、非現実的な動きをしてますよね。でも実際、中学生ってすごくエネルギッシュな時期なので、身体の動きも軽やかだった気がするんです。あれは、中学生の動きは主観的にああいう感じって、印象を再現したものかなと思ったんです。
中村:その通りです。若さの表現でもありますよね。作画という作為が、キャラクターの人間性や心情にも加担して、それを自然に誇張した動きにしたいと思ったんです。実はこの作品は動画枚数はそんなに多くなくて、4万枚ちょっとなんですよね。効率的に使っているから、よく動いてる印象があるかもしれないですけど。ただ、動画枚数に占める原画枚数が多目なんです。しかもいわゆるアニメの類型的なパターンにはまらない、難度の高い芝居の連続で。だから原画マンは大変だったと思いますが、だからこそ生まれる躍動感がある。それを生き生きと描いて頂けて、スタッフの皆さんには本当に頭が下がります。
氷川:柔らかさを強調する原画が随所に入ってないと、あんな動きにはならないですよね。目覚まし時計をはたくカットがお気に入りで、金属なのに思いきりしなって、電池までクニャッと一瞬折れて飛び出してくる (笑)。
中村:よく観ていただいてますね(笑)。でも実はあれはある種、リアルな動きでもあるんですよ。、たとえば野球選手がバットを振る時のリアルな動きをハイスピードカメラで撮ると、実際ものすごくしなってるんです。そうしたしなりを誇張してるだけのことなんですよね。実際にゆっくり動いてもらった動きを撮影したものと、速い動きをハイスピードカメラで撮影した動きは、まったく異なるものなんです。だから、実写でいかにワイヤーアクションを使って動きを誇張しても、2Dアニメのような動きとしての気持ち良さは出ないんです。僕の中で、アニメは実写の劣化した表現ではないという、強い思いがあって。アニメにはアニメの魅力がある、実写にはない魅力があるんだと強く言いたいんです。今回の映画はそれを凝縮した作品なんです。それをここまで挑戦的に、はっきり意志表明してる作品は、あまりないのかもしれないですけれど。
映像で体験・体感してもらう形で
作品全体から青春を感じてもらいたい
氷川:比較的リアルなものを求める傾向の現在の観客が、アニメならではのイメージを誇張した色彩や動きをどう受け取るか、興味津々です。
中村:今のアニメって、写真みたいな美術の上で、キャラクターの小さな動きで見せる作品が多いですよね。それをを見慣れたファンからすると、この映画を見ること自体に、ちょっとしたとまどいがあるはずだと思うんですよ。そういう意味では、この映画は2Dアニメのクラシカルな良さの延長線上にありながら、実は新鮮な体験ということになるのかもしれないなと。そうした部分でも、公開後のお客さんの反応にはドキドキしてます。
氷川:アニメは動きや色彩などビジュアルで、観客にキャラクターの感情を伝えるもの。それも気持ちが〈伝わる・伝わらない〉っていうことの一環ですよね。この映画の感想も、言葉にすると伝わる限界がありますが、「青春って輝かしくて恥ずかしい季節なんだな」と。こういう美しい彩りと伸びやかな身体で過ごした季節だったのかもしれない。それは失ったものではなく、今の自分の中にもあり続けているんだ。そう思えたことが貴重でした。
中村:僕の場合はそれを、青春という時代への、僕らの心の中にある願望として描きました。心の風景…というのかな。
実際には世界のどこにもないけれど、僕らの心の中にだけある風景であり、心の中にだけある時間としての「青春」――。
アニメという表現には、それが適していると思うんですよ。
僕は、「青春」という時代が誰にもあったとして、その最中にいる当事者は、実はそれをリアルタイムで感じることはないかもしれないと思うんです。
大人になって振り返った時に、ああ、あの時代が自分の青春だったんだなってわかる、そういう種類のものなんじゃないかと。
今の時代に、いわゆる青春ドラマの定型としての「青春」を描いたら、僕らがたちまちそれに胡散臭さを感じるのは、きっと僕らのリアルな実感からどこか遊離しているせいだと思うんですよね。
それを高校生のリアルな実感に即して描いたのが、『桐島、部活やめるってよ』みたいな映画で。これは非常にすぐれた映画で、実写の得意分野を生かしきってるという意味でも、すごい映画だと思うんですが。
でも僕は、アニメでならばむしろ、心の風景としての「青春」を描くべきだと思ったんです。
アニメでならば、それができるんじゃないかと。
でもそれは、言葉で「青春ってこういうものです」と説明してしまったら、必ず上滑りするものなんです。
それは言語化できない。だから映像としてしか表現できない。
この映画は、そういう挑戦だったんだと思うんです。
「青春」を理解してもらうのではなくて、体験してもらおうとすること。
つくり手側としては、それに真摯に向かいきったと思っています。
<完>