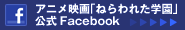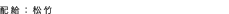[『ねらわれた学園』特別対談]中村亮介 × 氷川竜介 第三回
コミュニケーションというテーマをどう見せるか
今できることの結論として考えたこと――
氷川:大人になった自分の目から観て、思春期のいろんなことを思い返したり、あり得たかもしれない過去の想像力をかき立てられる映画でした。ただ現在のリアル中高生が観客とすると、かき立てられるだけの素地がまだまだ足りないかもしれません。そうした方たちに向けて、作どういうフックを考えられましたか? やっぱり恋愛の部分でしょうか?
中村:そうです、一つは恋愛ですね。それから、中学生を等身大に描くことで、自然なリアリティを感じてもらえればなと。アニメだと、「外見は中学生なんだけれど、内面は大人」みたいなキャラクターになりがちだと思うんです。そうならないように、実際の中高生が観て共感できるリアリティを目指したつもりです。大人目線の中学生像って、思い込みが多いなって気づかされるんですよ。で、中学生の目から見た中学生を描こう、と。たとえば大人から見るとみな一様に幼く見えても、中学生の頃にはすごく大人びて見えた同級生っていましたよね。それが女の子だと、彼女を見る自分の視線ってずごくエッチだったりして(笑)。そんな中学生の時の自分の感性も、思い出せるかぎり思い出して。卒業文集も読み返して、身もだえたり(笑)。でもそれを恥ずかしがらずに、恰好つけずに見せるように心がけたつもりです。あとは、テーマをどこまでわかりやすく見せるかですね。原作はファシズムがテーマですけど、今回のコミュニケーションというテーマは、見せ方がすごく難しくて。
氷川:そうですよね。それをどう解決しようと考えられたんですか?
中村:プランの段階で迷ったのは、中高生のお客さん向けに、もっとわかりやすくシンプルな結論を出して、なんというか……わかりやすく感動してもらうのか。それとも、その人たちが大人になってこの映画を見返した時にがっかりしないように、あくまで真摯に、今の自分に考えられるぎりぎりを提示すべきかで。それは映画の公開規模によってもかわると思うんですけど、今回は、今の自分の精一杯で描くことにしたんです。そのぶん、わかりやすさは犠牲になるわけですけど、考えさせるフィルムにはなるのかなと。なぜならこの年齢になっても、コミュニケーションがどうあるべきか、たった一つの結論なんて僕には出せなくて。僕もまだ考えているんです。そこに嘘をつくことは、この映画の主題にたいして誠実ではないと思いまして。
映画の登場人物たち・映画とお客さんの間にも
特殊なコミュニケーションがいろいろ存在する
氷川:なるほどと思いました。コミュニケーションの問題は、明解な答えを出さない方がよい性質のものなんですよね。
中村:映画の中でカホリも言いますけど、たとえば僕と氷川さんがこうして話していて、同じ言葉をやりとりしていたとしても、お互いが本当に同じ意味で使っているかどうか、厳密にはわからないですよね。そういう意味では、今コミュニケーションは、それこそテレパシーでもないかぎり、厳密には成り立っていないとも言えるんです。だからこのテーマは、そんなふうに虚無的に主題にすることもできるんです。でも僕はこの作品は、たとえ現実には心は通い合わないのだとしても、話そう、聞こうとすることにたいして、前向きでありたかった。僕ら人間がお互いに、本当の意味ではわかり合えないのだとしても、むしろ相手の心を知りたいと思う気持ちや、相手に自分の気持ちを伝えたいと思う気持ちこそが、かけがえのないものだと考えたいんです。
氷川:シェイクスピアの戯曲『真夏の夜の夢』からの引用は、その象徴なのでしょうか。
中村:はい。演劇の話を入れたかったのは、映画ってそもそも、あらかじめ決められたセリフをやりとりしている様子を、お客さんに観ていただくものじゃないですか。だから映画の中の登場人物のやりとりって、すごく特殊なコミュニケーションだとですよね。しかもスクリーンの中の、その「演劇」を鑑賞するって、考えてみればすごく不思議なものだなって。そんな映画と、お客さんの間にも、コミュニケーションがあるんだと思うんですよ。同じフィルムを見ても、映画とお客さんの間には、その数だけコミュニケーションが存在していて。お客さんひとりひとりが、どういう人間なのか、どういう人生を歩んできたかで、同じ映画から感じること、受け取ることがまったく変わってしまうんですよね。
新しいものと古いものが同居している江ノ島は
個性が求められる時代だからこそ決まった舞台
氷川:ところで舞台を江ノ島に選んだ理由は何だったんですか?
中村:江ノ電の沿線が舞台ですね。原作は物語の舞台を抽象的に描いてるんです。学校や街も、わざと抽象的な描き方をしていて。だからこの物語は、日本のどこでも起こりうるんだ、という印象を与えているんです。でも、作品ってそれが書かれた時代背景を背負ってるものなので。今の時代に抽象的に「ふつうの学校」とか「ふつうの街」を描こうとしても、具体的な像を結ばないんですよね。原作が書かれた70年代は、まだ社会全体がひとつの価値観や、皆でひとつの方向に向かう一体感を信じていた時代だったと思うんです。ある意味、そういう同調圧力こそが、その時代のファシズムだったのかな。一方で現代は、どんな人に対しても、個性的であることが求められてる時代で。それは過剰なほど、求められてると思うんですよ。
氷川:個性的であれと言われることが強迫観念のようになってないか、心配ですよね。
中村:そうです。それが一種の同調圧力になっていて。それこそが現代のファシズムといえば、そうかもしれないと思うんです。個々の価値観や好みは、違っていて当たり前。ひとりひとりはみんな別の人間――となると、人と人の関係性も希薄に感じられて。だからこそ〈絆〉っていう言葉が今の時代のキーワードになってる。どんなにコミュニケーションのツールが進歩しても、みんながいっしょうけんめい個性的であろうとすることで、かえって希薄化する関係性。それが〈絆〉を求める思いの、裏返しなんだろうなって思うんですよ。だから舞台となる街も個性的でないと、たぶん今の時代の作品と感じられないんじゃないかと。具体的に舞台をロケハンしてつくるアニメ作品が増えてますけど、たぶん根っこには、現代という時代にたいする、共通した同じ意識があるのかなって思うんです。
氷川:実は最近、江ノ島を舞台にしたアニメがたくさん作られいます。『青い花』、『つり球』、『TARI TARI』など、〈江ノ島アニメ〉というジャンルができつつあるのかなって、夏の講演でそんな話をしたばかりのときに、この作品がまた江ノ島で。(笑)
中村:江ノ島は自然もいいんですが、江ノ電(江ノ島電鉄)がまたいいんですよね。街の人々の暮らしとの距離が、すごく近くて。近すぎて、ほんとうに電車が民家の軒先をかすめて走ってますけど(笑)。線路によって街が分断されてる感じがなくて、文明の利器と古い時代からの人々の暮らしが、自然に一体になってる。鎌倉を舞台にしたのは、未来から超能力というテクノロジーが現代にもたらされるこの作品のストーリーと、それこそどこかで「繋がり」を感じていたのかもしれないですね。
第四回へ続く